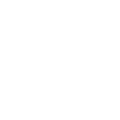経理部の松田です。
5月の連休に、長野県と山梨県へ出かけてきました。
出かけた目的は登山なのですが、登山口までは遠いので、1日目は移動日とし、2日目に登山をしてきました。
そして予定していなかった3日目に松本城を見学。
この3日間、私にとってはいずれも思い出に残る内容の濃いものだったので、ブログを3回に分けてお伝えします。
1日目は諏訪市の高島城見学と城門移築探訪です。
糸魚川ICで高速を降り、山道を進むと、車窓から見える風景は次第に変わっていき、遠くに見える山々のシルエットや、
木々の緑が広がる景色に心が和みます。
やがて視界が一気に開け、目の前に白馬連峰の山並みがドーンと姿を現す。
この瞬間は何度見ても、言葉を失うほど感動します。
雪を頂く山々は雄大で、空とのコントラストが見事。
その迫力と美しさに圧倒され、車を少し止めて景色を楽しみました。
白馬連峰の圧倒的な美しさよ!
さらに絶景の連鎖は続き、安曇野に向けて車を進めていると、鹿島槍ヶ岳や常念岳といった名峰が目に飛び込んできて、
壮大な山並みに視線が釘付けになりました。
さて本題へ。
ところで、皆さんは、古い城門が今もなお、お寺の境内に残っているのをご存知ですか?
実は、戦国時代や江戸時代の城門が、時を経て寺院に移築されているケースが多くあります。
その理由としては、戦国時代や江戸時代の城は、戦や火災で多くが失われましたが、
その城門や門柱は丈夫で立派なものであったため、時代を超えて別の場所で再利用されることが多かったのです。
特に、寺院の境内に移築されるケースが多く、歴史の名残を感じさせる貴重な遺構となっています。
古い石垣や門柱には、戦国時代の風格や当時の技術が感じられ、歴史好きにはたまらない発見があり、とてもワクワクします。
そういうわけで最初に訪れたのは長野県塩尻市にある「常光寺」。
松本から塩尻に続く山麓線沿いにあります。
常光寺は牡丹の花が有名なお寺だそうで、
訪れた時は、数輪の花が咲き始めたばかりの様子で花びらが陽光に映えてとても華やかでした。
こちらの山門が高島城から移築された城門です。
明治維新後、高島城が廃城になった際に「御殿門」が移築されました。
山門の前には一休さん。
境内には七福神や三猿など、さまざまな石像と置物などが安置されていて賑やかな境内でした。
常光寺が建つ丘陵地からの景色がとても綺麗で、思わず車を止めて写真を撮りました。
お次は諏訪市にある「温泉寺」へ。
こちらが高島城から移築された城門です。しかし城内のどこにあった門かは不明とのこと。
重厚な木造の門は、時代を超えた風格を漂わせていました。
また高島城にあった能舞台もこちらに移築されており、本堂として使用されています。
城門の佇まいと周囲の静かな境内が調和して、とても落ち着く場所でした。
織田信長が略奪したとされる梵鐘
武田領へ攻め入った織田軍が下伊那郡の安養寺の梵鐘を奪い、上諏訪まで引きずってきて捨てていったものを
諏訪家が温泉寺を創建した際に寺の梵鐘としたそうです。
梵鐘には引きずられてきた跡が見えます。
境内にある多宝塔です。
塔の中には、高島藩主忠恒が再造した鉄塔が奉納されています。
鉄塔は弘法大師が建てましたが、腐朽したため源頼朝が再興し、それを忠恒が石造で再造したものです。
塔の中を拝見することはできませんでした。
温泉寺は諏訪を治めた高島藩諏訪家の菩提寺です。
境内の奥へ進むと、歴代の諏訪高島藩主の墓所(国指定史跡)がありました。
中央の御霊屋は温泉寺を創建した2代藩主・諏訪忠恒のお墓、その周りに3代~8代藩主のお墓が並んでいます。
静かに佇む墓石の数々は、先人たちの時代背景や、その時代の人々の思いを想像させてくれます。
参道には樹齢約320年のしだれ桜が咲いていました。
「忠恒桜」の名がついたこの桜は諏訪忠恒が大坂夏の陣に出陣した際に持ち帰って植えたものだそうです。
温泉寺には平安時代の歌人・和泉式部のお墓もありました。
城門のほかに思わぬ史跡もあって、とても楽しめました。
高島城へ。
諏訪市役所の駐車場に駐車しました。無料です。
市役所がある場所はかつての南の丸跡。南の丸は高島藩が江戸幕府の罪人を預かった場所です。
この駐車場の一角に徳川家康の6男・松平忠輝の祠がありました。
忠輝は家康に勘当されて諏訪へ流刑され、高島城南の丸で過ごしました。
祠の前の参道橋は「諏訪鉄平石」の一枚岩です。
説明書きには、霧ヶ峰周辺で産出された石を諏訪鉄平石と言い、鉄のように固く平らであることが名前の由来と書かれていました。
天守閣を見学。現在の天守閣は昭和45年に復興されたものです。
慶長3年(1598)に豊臣秀吉の家臣・日根野織部正高吉により築城され、諏訪氏の居城として270年間、その威容を誇ってきました。
お城は諏訪湖の湖水に囲まれ、「諏訪の浮城」と呼ばれていたそうです。
明治8年(1875)に廃藩置県により天守閣は撤去。しかし、市民の熱意によって昭和45年(1970)に高島城は復興されました。
1・2階は郷土や高島城の資料室、3階は展望室になっています。
昔、お城は諏訪湖に面していたので、難攻不落のお城だったようです。
南へ目を向ければ富士山の姿が!
城内は「高島公園」として開放され、市民の憩いの場となっています。
八重桜が咲いていました。
冠木門
冠木橋から見た景観がこちら。
ここは川渡門跡で、現在は三の丸にあった御殿の裏門が移築されています。
昔はここから舟に乗って湖へ出ていました。
多門跡
諏訪家の家紋「梶の葉」
本日最後に訪れたのは茅野市にある「宗湖寺」
宗湖寺は高島藩初代藩主・諏訪頼水の父・諏訪頼忠の菩提所です。
こちらの山門は高島城三の丸御門が移築されています。
明治天皇が巡幸でこちらに訪れた際に、この井戸水でお茶を出しておもてなしをしたそうです。
お寺の奥の方に公園らしきものが見えたので行ってみると、木落し公園がありました。
諏訪大社の御柱祭で、御柱を坂の上から下へ滑り落とす「木落し」が行われる場所です。
御柱祭は、7年に一度、寅と申の年に行われる1200年続く伝統神事。御柱に使われるのはモミの大木だけだそうです。
見晴らしのよい丘陵地にあり、鉄橋の右先は茅野駅です。
これにて本日の城門探訪は終了。
城門が移築された寺院巡りは、歴史の宝探しのような楽しさがあります。
移築された城門は、ただの遺構としてだけでなく、その場所の歴史や背景を知るきっかけにもなり、
案内板や資料を読むことで、当時の城の役割や戦いの様子、移築された経緯などを学ぶことができ、歴史への理解が深まります。
私は、福知山城や田辺城、飯山城の城門の移築先も訪れているので、いつの日かご紹介できればと思います。
国道20号線を韮崎方面に向けて進んでいると見えてくるのが「七里岩」
延々に続くこの断崖は、八ヶ岳の山体崩壊による岩屑なだれによってできたものです。
自然が生み出したこの景観、いつ見ても凄いです!
崖上の台地には、甲斐国の武将・武田勝頼が築城した新府城がありますよね。
随分前に訪れていますが、また行ってみたくなりました。
そして、徐々に視界に入ってきたのは富士山の壮大な姿!
久しぶりの富士山、その姿はやはり圧巻です。
雪をまとった富士山の頂。空の青と雪の白、そして山の深い緑が織りなすコントラストが心に響き渡りました。
運転しながらも、目はひたすらに富士山に釘付け。
窓越しに見えるこの絶景は、日常の喧騒を忘れさせてくれる特別な瞬間でした。
2日目につづく。