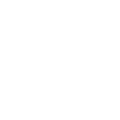経理部の松田です。
昨年に続き、今年も桜咲く季節に京都へ行ってきました。
京都の春は、まさに絶景の連続。歴史と自然が織りなす風景に心が奪われました。
今回訪れた場所は、平安神宮、永観堂、南禅寺、知恩院、八坂神社の5カ所の神社とお寺です。
誰もが知る名所ばかりですが、桜と調和する景観はさらに美しく、神聖な雰囲気が一層引き立っていました。
そのほか、道中にあった歴史上人物ゆかりの遺跡なども見てきました。
岡崎公園の駐車場に車を1日駐車し、徒歩でぐるりと廻ってきました。
歩いた歩数は3万歩。途中で携帯電話の充電が切れてしまったので、正確なアプリの歩数は把握できませんが、
実際はそれ以上歩いてます。
## 1. 平安神宮
まず最初に向かったのは、平安神宮。
平安遷都1100年を記念して、明治28年(1895)に第50代桓武天皇を御祭神として創建されました。
シンボルにもなっている大鳥居、朱色の大鳥居が印象的です。
正面の応天門前の左手に置かれているのは、日本最初の電気鉄道電車。重要文化財に指定されています。
こちらが応天門。
拝殿である大極殿は修復工事中。
外観は拝見することはできませんでしたが、中に入ることはでき、参拝してきました。
平安神宮は明治28年に創建されてから、令和7年の今年は御鎮座130年の式年を迎えます。
それに伴い、伝統文化財の維持保存のために、順次修復されているようです。
総事業費14億5千万円、奉賛予定額4億円。金額に驚きです。
右が蒼龍楼、左が白虎楼。
大極殿の前に植えられているのは、左近の桜と右近の橘です。
蒼龍楼を背景に、皆さん熱心に桜を撮影されていました。
参拝が終わったら、平安神宮神苑へ。
平安神宮は桜の名所としても知られていて、神苑には約300本の桜が咲いているそうです。
神苑は、社殿を取り囲むように東・中・西・南の4つの庭からなる広大な池泉回遊式庭園です。
今回初めて、神苑も見てきました。
谷崎潤一郎の「細雪」にも登場する紅しだれ桜。優美な姿に思わずうっとり。
ソメイヨシノやしだれ桜など境内のいたるところで異なる種類の桜が楽しめます。
池に浮かぶ飛び石の「臥龍橋」
これを見ると渡らずにはいられません!
街なかにあるとは思えない静けさ。
桜以外にも、さまざまな花が咲いていました。
神苑の中でも一番広大な庭園が東神苑。
静かで厳かな空気の中、心が洗われるような時間でした。
泰平閣を渡ります。泰平閣から見る庭園も美しかったです。
泰平閣を渡ると、結婚式の写真撮影が行われていました。
こちらにある石柱は、豊臣秀吉によって作られた三条大橋と五条大橋の橋脚に使われていたものです。
先ほど渡った臥龍橋も同じ石柱が使われています。
石柱を過ぎると、神苑の出口です。
白虎楼から入場して蒼龍楼から出てきました。
平安神宮前にある岡崎公園ではイベントが開催されていて、沢山の方が訪れていました。
猿回しやよさこい踊りが行われていたり、屋台の出店もあって非常に賑やかでした。
京セラ美術館。
モダンなデザインと伝統的な京都の風情が融合した美しい外観が印象的です。
館内には入りませんでしたが、外から眺めるだけでも、その洗練されたデザインと周囲の自然との調和に心惹かれました。
大鳥居の前に架かる橋から見渡す琵琶湖疏水の眺めも良いです。
琵琶湖疎水は京都の歴史的な水路であり、琵琶湖から京都へと水を引くために作られたものです。
こちらの桜並木も圧巻。屋形船が風情を感じます。
春のこの季節は、桜や新緑が美しく、静かな流れとともに心が癒されました。
京セラ美術館の隣は「京都市動物園」
動物園の横を通って永観堂に向かっていると「白河院址」がありました。
もとは藤原良房の別荘で、藤原一族によって代々受け継がれてきたのですが、平安時代に白河天皇に献上し、
白河天皇によって法勝寺が建立された地です。
現在、白河院の遺構はほとんど残っていませんが、当時の庭園や建物の一部は、京都市内の史跡として保存されています。
## 2. 永観堂
次に向かったのは、永観堂。正式には禅林寺といい、仁寿3年(853)の創建です。
こちらは秋の紅葉で有名ですが、春の桜も見事でしたよ。
建物は本格的な書院造り。
堂内は長谷川等伯や狩野派の華やかな襖絵で飾られており、とても見応えがありました。
各お堂は渡り廊下でつながっており、多彩な庭園が点在。
まるで絵画のような風景に写真を撮る手が止まりませんでした。
堂内は撮影禁止ですが、庭園撮影はできました。
境内で最も高い場所にあるのが多宝塔です。
こちらは、外から見た阿弥陀堂。
豊臣秀吉の息子である豊臣秀頼により、慶長12年(1607)に大阪の四天王寺から移築された建物です。
阿弥陀堂に祀られているのは、お顔をななめ後ろに向けている珍しいお姿の「みかえり阿弥陀」です。
後方を振り向く姿は、「思いやり深く周囲を見つめる姿勢」「愛や情けをかける姿勢」「遅れた者たちを待つ姿勢」など
慈悲の姿が現されているそうです。
撮影はできませんが、穏やかな優しいお顔が印象的でした。
開山堂へと向かう階段状の回廊が「臥龍廊」
山の斜面に沿って作られていて、1本の釘も使われていないんだそう。
桜の花びらが風に乗って、廊下に舞い散る様子もまさに絶景でした。
甘茶が用意されていたので、庭園を見ながら暖かいお茶のひとときを楽しみました。
建物の外へ出て、石段を上がって多宝塔へ。
そこは京都の街並みを一望できる絶景スポットでした。
多宝塔が建つ場所はスペースが狭く、ここからは多宝塔全体を写真に収めることは出来ませんでした。
下に降りて境内を散策。
こちらは「勅使門」。天皇の使者・勅使が寺院に参向した際に出入りに使われる門です。
御影堂
この放生池の周りや、境内のいたる所に紅葉が植えられていたので、秋にも一度訪れてみたいところです。
放生池越しに多宝塔を撮影。
絵になりますね 。
暖かい陽光とさわやかな風に包まれながら、春の京都の風情を存分に味わいました。
お次は、新島襄と八重のお墓へ。
京都の風情ある散策路「哲学の道」。
哲学の道に到着すると、木々に囲まれた小さな鳥居と石段が見えてきます。
そこが熊野若王子神社。
境内はこぢんまりとしていますが、永暦1年(1160)に後白河天皇が永観堂の守護神として造られた神社です。
熊野若王子神社を通り過ぎ、山道を登ります。
かなりの急坂です。
階段で整備されていますが、登り口でお助け杖をお借りました。
登ること20分、お墓に到着。
新島襄は同志社大学の創設者。
お墓はシンプルながらも、静謐な空気に包まれており、彼の志と努力を偲ぶことができました。
隣には、妻の八重の墓。
八重は幕末の会津藩で砲術師範の娘として会津戦争を戦った「幕末のジャンヌ・ダルク」と呼ばれた方です。
この場所に立つと、彼らが歩んだ激動の時代と、その中で揺るぎない信念を持ち続けた姿が目に浮かびます。
静かに手を合わせながら、未来を切り拓いた先人たちの思いに思いを馳せました。
この日は同志社の女子学生の方が沢山訪れていて、お墓を清掃されていました。
お借りした杖はこちらで返却しました。
次は南禅寺へ。道中にあったのが、東山高校。
バレーボール日本代表の高橋藍選手や、サッカー日本代表の鎌田大地選手などを輩出している有名校。
周辺には観光名所が沢山あり、歴史的な街並みや自然に囲まれた環境で学ぶことができるのはいいですね。
水の流れがきれいだったので、立ち止まって撮影。水の流れに潤されます。
##3. 南禅寺
南禅寺は京都を代表する禅寺の一つ。
正応4年(1291)に鎌倉時代の禅僧・無関普門(むかんふもん)によって創建されました。
室町時代には、足利義満によって大規模な伽藍の整備が行われ、京都の禅宗の中心地として発展しました。
大寂門をくぐって南禅寺の境内へ。
国宝「方丈」や、「三門」をはじめとした重要文化財、国名勝の方丈庭園など、境内には見どころが豊富です。
まずは重要文化財の三門。
大坂夏の陣で戦った武将や兵士の慰霊のために藤堂高虎により寄進された門です。
高さ22メートルの巨大な三門は、重厚感のある威風堂々とした佇まいです。
南禅寺の象徴とも言える存在ですね。
三門の楼上に上がることもできます。
石畳の道と桜のコントラストが印象的でした。まさに絶景。
歌舞伎「楼門五三桐」で天下の大泥棒・石川五右衛門が発した名セリフ「絶景かな、絶景かな」は有名です。
こちらは法堂。
天井には画家・今尾景年による幡龍の絵が掲げられていました。
満開の桜が境内を彩り、美しい。
方丈を拝観。静寂な雰囲気が漂います。
狩野探幽作の「水呑みの虎」をはじめとする襖絵は見どころありました。
風情溢れる枯山水庭園。
縁に腰を下ろして、美しく手入れされた庭園をゆっくりと眺めたいところですが、
まだまだ見たいところがいっぱいあるので先を急ぎます!
赤レンガのアーチ「水路閣」
ここだけ近代的な香りが漂う、ノスタルジックな景観。
人気スポットなので観光客を写さないで写真を撮るのは難しいですね。
南禅寺の境内にある「天授庵」
ここも庭園で有名。枯山水と池泉回遊式の2つの庭園があります。
建物内部は拝観できませんが、お庭を見て廻ることができます。
多くの方が縁側に腰かけて、景色に見入っていました。
池に黄金色の鯉が! なにか良いことがありそう♪
山名宗全(やまなそうぜん)のお墓がある「真乗院」
山名宗全は室町時代の武将であり、応仁の乱で細川勝元と11年間にわたり対立した人物です。
この応仁の乱の兵火により、南禅寺は寺全体が焼失してしまったのです。
その後、 徳川家康の側近・以心崇伝(いしんすうでん)により南禅寺は再建されました。
中には入れなかったので、門の前にある石柱を撮影してきました。
最後に「金地院」も見てきました。
もともとは室町時代に足利義持が創建。その後、慶長10年(1605)に南禅寺の住職・以心崇伝が復興・再建した
お寺です。
建物は伝統的な建築様式で禅の精神を感じさせる落ち着いた空間でした。
石畳を進んでいくと東照宮があります。
こちらが東照宮。
徳川家康の厚い信頼を得ていた以心崇伝。東照宮には家康の遺髪と念持仏が納められています。
天井には狩野探幽による「鳴龍(なきりゅう)」が描かれていました。
手を伸ばして撮ってみたけど、上手く撮ることはできず。
静謐な風景が広がる特別名勝の「鶴亀の庭」
今日はいくつもの庭園を見てきましたが、一番心が落ち着ける場所だったかも。
「この門を入れば 涼風おのづから」
境内を歩きながら、歴史の重みと春の息吹を感じることができた南禅寺。
これにて南禅寺を離れ、次の目的地へと向かいますが、記事が長くなってしまったので続きは次回に。
京都の歴史的なスポットを巡った旅の思い出はまだまだ続きます!