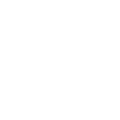経理部の松田です。
前編の続き
2日目も奈良の世界遺産巡りです。
その前に、JR奈良駅からほど近い伝香寺へ寄りました。
伝香寺は戦国の名将・筒井順慶の菩提所となっているお寺です。
筒井順慶は戦国時代に大和を統治し、織田信長の命により郡山城を築城。
前回のブログで登場した嶋左近が最初に仕えていた方です。
拝観時間は9時からなのですが、8時半に着いてしまって…
係員に「どこから来たの?」と聞かれ、「金沢からです。筒井順慶の供養塔を見に来ました」と答えると、
「遠くから来たね、今開けてあげるよ」と。
係員に案内されながら境内へ入っていくと、すぐに筒井氏の五輪塔が建っていました。
奥へと進み、鍵がかかった建物の扉を開けて見せてくれたのが、
通称「はだか地蔵尊」として親しまれている裸形地蔵菩薩立像(重要文化財)です。鎌倉時代の作。
衣の着せ替えは1228年より毎年7月23日に行われているとのこと。
監視カメラ付きの厳重な扉にビビりましたが、「写真撮っていいよ、ゆっくり見ていって」とおしゃってくれ、
普段は拝見できない貴重なものを特別に見せてくれました。
写真には写っていませんが、伝香寺の本堂は1585年8月11日に筒井順慶の一周忌に建立された仏殿です。
中に祀られている釈迦如来座像は、京都方広寺の大仏のモデルとなった仏像なんですって。驚きです。
花は咲いていませんが、こちらは奈良三名椿の一つ「散り椿」。
通常の椿と違って、花びらが一枚づつ散ってゆくとのこと。係員さんが色々説明してくれてました。
お次は春日大社へ。
道路には『鹿注意』の標識。鹿が飛び出してくる可能性があるので注意して運転を!
春日大社もまた奈良を代表する世界遺産。
約1300年前の奈良時代に平城京の守護と国民の繁栄を祈るために創建されました。
鹿は春日大社の「神鹿」です。神様の使いですよ!
春日大社の主祭神である武甕槌命(たけみかづちのみこと)は、鹿島神宮(茨城県)から白鹿に乗って
奈良にやって来たという言い伝えから、奈良の鹿は神様の使いとされています。
「もののけ姫」に出てくる「シシ神」のようです。
鳥居をくぐると伏鹿手水所があり、ここで手と口を清めてから参拝します。
隣には祓戸神社。境内には小さな神社がいくつもありました。
両脇にずらりと並ぶ石燈籠。美しい景観です。
石燈籠の間から鹿がひょっこり。まるで、もののけの世界。
森の中をゆっくりと巡り、階段を上がると南門。
そして鮮やかな朱塗りの社殿へ。
眠れないことがあります。
不意に、漠然とした不安におそわれて。
現代人にストレスはつきものだけど、毎日がストレス、憂鬱、怒り、不安の連続。
欲望と願いは尽きないけど、敢えて何も願わず無の心で手を合わせてきました。
ですが何を思ったのか、人生初のおみくじを引いてみたら、なんと大吉ゲット!
\これって運命の扉が開いたってこと?!/
あまりにも都合のいい解釈ですが、とりあえず後悔のない日々を過ごしていこうと思います…。
西回廊を歩いて社殿の外へ。
回廊の途中にあったのは八雷神社。
本殿の鬼門を守り、八大龍王の力により雷と黒雲を自由に扱う神様。人々の願いを叶えられる神様です。
他にも境内を歩いていて出会った神社が以下4つ。
総宮神社
住まいを授け、住む人の平安をお守りくださる神様です。
一言主(ひとことぬし)神社
ひとつだけ願いを叶えてくださる神様。願い事が沢山あって一つに絞り切れないなぁ。
龍王社
運気を上昇させ富貴に導く神様。
水谷神社
医薬の神として病気平癒や福徳円満をもたらす神様。横に伸びる大樹はイブキの木です。
境内では多くの鹿にも出会います。
鹿せんべい売場の前で客を待つ鹿たち。
鹿せんべいを手にした途端、鹿が群がってきます。
私も鹿せんべいをあげてみたら、鹿に囲まれて身動きがとれなくなってしまいました。
〝早くくれ″と言わんばかりに突進されたり、引っ張られたり。
〝待って待って″と言っても通じやしない。鹿に甘く見られてしまったのか?!
めっちゃ懐いてるやん!
かわいいバンビちゃんの姿も。
おせんべい欲しいのに、大きな鹿の前では遠慮気味で後ずさりしてました。
めちゃくちゃ可愛かった!
鹿たちは人懐っこいけど、野生動物なので優しく接してあげましょう。
なんせ神様の使いですから。
境内にある国宝殿も見てきました。
春日大社が所有する国宝や重要文化財を所蔵する美術館です。
これは舞楽演奏に用いる日本最大の鼉太鼓のレプリカ。
本物の国宝は2階に展示されていました。鎌倉時代の作。源頼朝が寄進したんだそう。
ということで、春日大社の神秘的な空気を感じた後は次の目的地へ!
途中、平城宮跡の「朱雀門」前を通過。今回は時間がないので寄りませんでした。
向かうのは西ノ京エリア。
奈良へ来たら忘れてならないのが唐招提寺。(個人的に)
南大門の前から中を覗いたら、天平時代の風がフワッと舞い込んできたー。
なんだかタイムトラベルした気分!
唐招提寺は、苦難の末に来日を果たされた唐の高僧・鑑真和上が、759年に仏教を学ぶための修行の道場として
建立しました。
正面に荘厳な姿を見せる金堂は、奈良時代建立の現存するお堂です。
唐招提寺には、金堂をはじめ、講堂、鼓楼、経蔵など創建当初の建物(国宝)が多く残っています。
印象的なのは、スッと空に伸びる大屋根と整然と並んだ8本の柱たち。
修学旅行で訪れた時にこの美しさに感動し、それ以来ずっと記憶に残っていました。
金堂の中は撮影禁止。
本尊は盧舎那仏坐像、左右に薬師如来立像と千手観音立像が並んでいました。いずれも国宝です。
講堂(国宝)
鼓楼(国宝)
経蔵(国宝)。日本最古の高床式の校倉です。
宝蔵(国宝)
鑑真和上の墓所は境内の奥まった場所にあります。
塀は土と瓦を交互に積まれたような造り。
門をくぐると苔で覆われた神秘的な空間が広がっていました。冬なのにふかふかな緑が美しいです。
立派なお墓です。
そしてお墓の横に『天平の甍 井上靖』と刻まれた石碑が!
井上靖の小説が大好きな私はテンションが上がりました。
小説『天平の甍』は、奈良時代に4人の留学僧が遣唐船で唐へ渡り、鑑真を苦心のすえに日本に招いてくる経緯を
描いた小説です。
当時は船で海外に行くことは命がけ。6度にもわたる挑戦で訪日をはたす鑑真の苦難の道が描かれています。
何度も写真を撮っていたら、外国人観光客に〝これは何?″と英語で尋ねられ、
指をさしながら〝テ・ン・ピ・ョ・ウ・ノ・イ・ラ・カ″と答えた私。
その意味を上手く説明できなくて、英語力のなさに落ち込みました。⤵⤵⤵
こちらは修復された開山堂。鑑真和上御身代わり像が安置されています。
撮影禁止なので屋根だけ撮影。青空がとても綺麗だったー。
自然に包まれた静かな境内
境内に咲いていたサザンカ。
透き通るような白い花びらが綺麗でした。
金堂の屋根の連なりが本当に美しい。
この魅力的な姿、心をわしづかみにされちゃいますね!
天平時代の面影が残る唐招提寺。
いくらでも眺めていられるほど、この佇まいが好きです。
世界遺産巡りの最後は薬師寺へ。
唐招提寺からは徒歩15分程。「歴史の道」を歩いて向います。
北門から境内へ。
薬師寺は680年に天武天皇が皇后(後の持統天皇)の病気平癒を祈願して建立しました。
しかし度重なる災害によって諸堂は焼失し、現存するのは東塔だけ。再建されたのは、1976年(昭和51年)のことです。
比較的最近の再建ですが、それまでには大変な苦労があったんですよ。
まずは食堂内へ入っていくと、金堂に祀られている薬師如来の台座のレプリカが置かれていました。
金堂内は撮影禁止なのでこちらで写真を撮っておきます。
こちらは大講堂。大きくて立派です。
境内の中央にあるのが金堂。長い時を経て、創建当時の姿に復興されました。
創建当時、壮麗な姿は「竜宮造り」と呼ばれていたそうですが、まさに竜宮城そのものです。
堂内には本尊の薬師三尊像と吉祥天女画像が祀られていました。どちらも国宝。
ちょうど僧侶による説明が行われるということだったので聞いてきました。
話の後半はお守りなどの宣伝でしたけど面白かった!笑
石川県穴水町と薬師寺とは昔より縁が深く、毎年、穴水町からもち米が奉納されているとのこと。
しかし昨年は地震で被災したため無理だろうと思っていたそうですが、約1.2トンものもち米が穴水町から届いたそうです。
薬師寺では、このもち米でお餅を作って1袋600円で販売しており、売上の全額を被災地に届けるとのお話がありました。
まさかここで同県民の穴水町の話が聞けるなんて!
厳しい状況下でありながらも穴水町の奉納に込めた想いを知り、苦境に負けない穴水町の底力を感じて胸が熱くなりました。
そして、私たちの知らない所で参拝者に呼びかけながら支援をしていただけることがとてもありがたいです。
金堂の手前には2つの三重塔。
塔の中に、お釈迦様の生涯をあらわした釈迦八相像が安置されていました。
こちらは西塔
東塔(国宝)は730年に建てられた薬師寺で唯一現存する奈良時代の建物です。
中門と色彩が美しい二天王像。
一旦、南門から境内の外へ出て休ヶ岡八幡宮を見てきました。
こちらは薬師寺の「守り神」で、1603年に豊臣秀頼により建てられたもの。
最初に休ヶ岡八幡宮にお参りをし、身を清めてから薬師寺に参拝するのが良いらしいです。
珍しい造りの社殿。とても美しいです。
見ておいて良かったー
薬師寺南門から。
再度、薬師寺の境内の中を通って唐招提寺の駐車場へ戻ります。
拝観チケットを受付で見せれば再入場できます。
最後に玄奘三蔵院伽藍を見て奈良を後にしました。
豊かな自然に包まれた境内、自然の中で悠然と生きる鹿たちの姿、歴史を感じられる街並みなど
今回の奈良の世界遺産巡りは1300年の歴史を体感した旅となりました。
若い頃とは見えるもの、感じるものが違った今回の奈良旅。
2日かけても足りないほど魅力的でした。